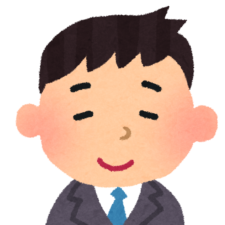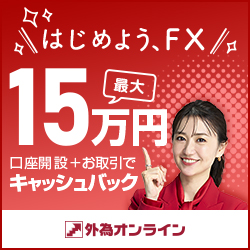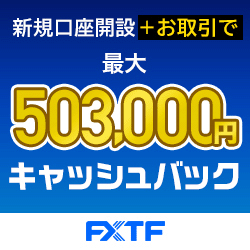MSワラント債と転換社債(CB)の違いとメリットデメリットについて
よく、転換社債とワラント債について混同して
しまうケースがあります。
紛らわしさを避けるために、ワラント債は、新株引受権付社債
と明記するケースが多くなっています。
そこで今回は、転換社債とワラント債について整理してみたい
と思います。。
MSワラント債とは
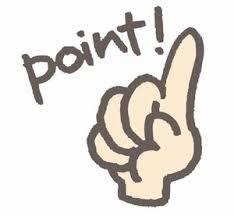
今回はMSワラント債を取り上げますが
その前にシンプルにワラント債について
解説してみたと思います。
発行会社の株式を一定の価格(行使価格)で、定められた期間内(行使期間)に、
取得できる権利を持つ有価証券のことをいいます。
ワラント債は、「株を購入する権利を有していて、権利を行使する際には、
行使価格を支払う必要がある」ため、完全に債券と分離されている考え方になるので
ワラント債の価格 = 債券価格 + コールオプションの価格
となります。また債券部分と株式の購入権利部分は分離しています。
転換社債は、株式に転換するときに社債と交換になります。一方で、
ワラント債は「権利を持っているだけ」なので、行使するときは別途費用
が必要になりますが、社債は手元に残ります。
ワラント債がすべて権利行使された場合の、「株式の希薄化」が問われていて
希薄化率(EPSベース)= 希薄化後EPS ÷ 希薄化前EPS
となります。
希薄化後EPS = 純利益 ÷ (既発行株式数 + ワラント債による発行株式数)
ワラント債による発行株式数 =調達金額(債券発行額)× 付与率 ÷ 額面
と算出します。
上場企業が資金調達をする方法は、一般的に2種類あります。1つは、
新たに株を発行して投資家から資金を集める「公募増資」、もう1つは
銀行借入です。 しかし、赤字が続く企業は信用力が落ちているので、
これらの方法では資金調達ができません。
そこで、やむを得ず特典をつけて、買い手(引受先)が
お得になる条件をつけた、株を買う権利を発行します。
これが「MSワラント」です。MSワラントとは、「Moving Strike Warrant」
の略で、日本語に直すと「行使価格修正条項付新株予約権」です。
要約すると、「前日の株価終値よりも安い価格で購入できるように、
購入価格を修正する新株予約権」となります。
つまり、前日終値が1,000円の日は900円で新株を購入できる仕組みです。
MSワラントを引き受けるのは主に証券会社なので、
証券会社にとって有利な条件を付けたものとなっています。
MSワラントの仕組み
①株価1,500円の会社が、「発行価格決定日の株価×0.9」で、
証券会社に対してMSワラントを発行することを発表
②証券会社はMSワラントで手に入れる予定の新株1,000株分だけ
空売りして、MSワラントの発行価格決定日までに株価を1,500円から
1,000円に下げておく
③発行価格決定日の株価1,000円をもとに発行価格が900円に決まり、
証券会社は900円で新株1,000株を手に入れる
④空売りの返済に、900円で手に入れた新株を充てる
⑤証券会社は、600円(=1,500円 – 900円)×1,000株=60万円
の利益が手に入る
このように、証券会社は最終的に利益を確実に手に入れることになりますが
既存株主にとっては、株価が1,500円から1,000円に下がるため、
1,000株持っていた場合には、500円×1,000株 の損をします。
さらに、証券会社が新株を取得した直後に株式市場で売ってしまうため、
株価が下がってしまいます。
また、発行済み株式数が増えることで、「1株あたりの利益」が
小さくなってしまう(希薄化する)ため、「1株あたりの利益×市場の期待(PER)」
で計算される株価が下がっていきます。
転換社債(CB: convertible bond )とは
発行時に決められた値段(転換価額という)で株式に転換することができる債券です。
債券の発行後に株式に転換するか、株式に転換せずに利金や償還金を受け取るかを
選択できます。株式と債券の二つの特徴をあわせ持つ商品です。
転換社債は、「債券としての価格」と「株式としての価格」の2つを持つことになります。
債券としての価格はクーポン・償還価額の割引モデルで、株式としての価格は
配当割引モデルとかで評価し、なぜか株式としての価格は「パリティ」と呼ばれます。
株価が上がった場合、株式に転換すれば、株価の値上がり益を享受できますし、
株価が下がった場合、債券としての価格が転換社債の価格を
下支えすることとなります。
また、転換社債は「株式に転換する権利」を有していることと
同義なので、コールオプションの性質を有していて
内在するコールオプションの価格 = 債券の時価(市場取引価格) – 債券
としての価格で評価することもできます。
またよく出てくるのは「乖離率」ですが、理論上「転換社債の理論価格=パリティ」
と定義されており、時価と理論価格を比較して、
値ごろ感を判断するための指標のようです。
乖離率 = (転換社債の時価(市場取引価格)- パリティ)÷ パリティ
と表され、乖離率がプラスだとお買い得とのことです。
「MSワラント」と「公募増資」の比較
MSワラント のメリットとデメリット
一番の問題は、MSワラントをおこなうと、公募増資をおこなったときよりも
株価が下落することです。理由は、MSワラントの場合、株を取得したら保有せず、
すぐに市場へ売ってしまうからです。市場に出回る株数が増えるため、
株価が下落します。
さらに、資金調達にも差がでます。例えば、企業が100株発行したとします。
公募増資の場合、株価が1,000円だと10万円の増資となります。
しかし、MSワラントの場合、株価が1,000円でも「1割引」
の特典をつけていたら、9万円分しか増資できません。
公募増資は、増資があった直後は株式の希薄化が起きるため株価が下がります。
そのため、短期的にみれば既存株主に損がでます。しかし、企業は公募増資で
調達したお金を使って投資をするため、長期的に見て、
その投資がうまく行けば、企業の価値が上がっていき、
株価上昇にもつながります。
まとめ
ワラント債は、新株引受権がついている債券で
社債の部分とそのオプションの部分は切り離して
考えるべき商品です。
ワラント債の価格 = 債券価格 + コールオプションの価格
となります。
一方で転換社債は、発行時に決められた値段(転換価額という)
で株式に転換することができる債券です。
債券の発行後に株式に転換するか、株式に転換せずに
利金や償還金を受け取るかを選択できます。
株式と債券の二つの特徴をあわせ持つ商品です。
この二つの商品については、混同しやすいですが
両方とも発行体の資金調達の手段であり、発行体の既存株主に
とっては稀有化してしまうために、デメリットのほうが大きいと思われます。