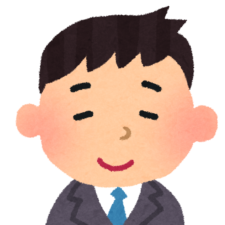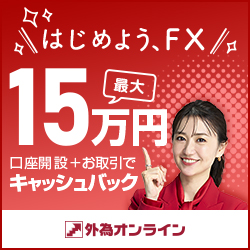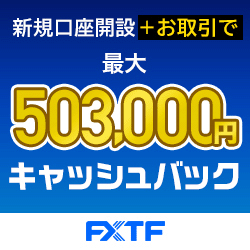日本の国債市場の終焉?市場原理と逆行し長期金利価格を管理下におこうとする日銀の金融政策
ダッチロール状態の日銀の金融政策
日銀金融政策決定会合の内容は矛盾した二つの政策を
組み合わるという理解しがたい内容となりました。
不人気な量的緩和から身を引くような政策を打ち出しながら、
その後退などないという趣旨の言説を組み合わせています。

10年国債利回りをゼロに
日銀の新たな政策の柱は、10年物国債利回りをゼロに
誘導するために必要なだけ債券を買い入れることです。
その半面、長期国債の買い入れ額を年間80兆円に据え置きつつ、
金融緩和を「強化する」とするという矛盾した政策を打ち出しています。
これら二つの目標は矛盾する。例えばりんご売りが栽培農家に対し、
1キロ当たり50円の市場価格を維持するのに必要なだけりんごを調達
すると言いながら、年間80トンの買い付けを宣言することを考えて
みてほしい。需要で値上がりし、約束の80トンに達する前にバナナの
価格が100円になってしまったら一体どうするのだろうか。
日銀が本気で新旧の政策を並行して進めるつもりなら、似たような
ジレンマに陥るだろう。10年物国債は日本の千数百兆円に上る債券市場の
ベンチマークです。需要が急激に縮小すれば、利回りをゼロに維持するために
年間80兆円より多く買い入れる必要に迫られるが、そのときはどのように
するのでしょうか。
黒田総裁は会見で価格維持優先とのこと
黒田総裁はこの矛盾を説明する上で、実質的に年間80兆円の国債買い入れ目標
を否定しました。実際の買い入れ額の「増減はあり得る」と記者会見で述べ、
弁明の余地を作り出しました。りんご売りの例で言えば、本当に実現したいのは
1キロ当たり50円の価格であり、後はそれほど重要ではないとのべ、事実上
ベンチマークである長期金利の水準を日銀がコントロールすることを
宣言した格好です。